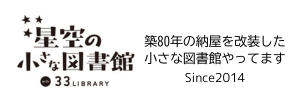いすみの福祉施設「ピア宮敷」で梨の花粉作り 農福連携で農家支える

いすみの社会福祉法人「土穂会」が運営するピア宮敷第1工房(いすみ市岬町桑田)で4月9日、梨の花粉作りに向けた作業が行われた。
同市岬地区では梨の栽培が盛ん。特産品として7月下旬から8月中旬ごろまで、特設販売所を開き多くの人でにぎわう。例年、4月上旬ごろ、花が開花し、手作業で花粉を付ける交配作業が始まる。梨の花から花粉を採取するのは大変手間で、安価な輸入花粉に頼っていたが、病気の流行に伴い2023年に輸入が禁止。国産花粉の確保が課題となっている。
同施設では、ナバナの収穫など農作業を通した「農福連携」を積極的に進めている。地元の梨農家から「手が足りず花粉採取作業を自分たちですることができない。手伝ってもらえないか」という相談を受け、昨年、取り組みを始めた。
梨の花の開花は1週間から10日ほど。その期間に花を摘み取り花粉を採取する。同施設支援員の石野健太さんは「花の摘み取り後、すぐに開葯(やく)作業をしなければならないため、多くの人の手が必要となる。天気や開花の状況もあり予定が立てづらいが、柔軟に対応できるメンバーと共に、今年も取り組んだ」と話す。
当日は、15人ほどの利用者と共に梨農園に行き、1時間30分かけて約10キロの花を摘み取った。持ち帰った花を、葯採取機を使い花と葯に分離する葯取り作業を行った。最終的に手作業でふるいにかけた葯を乾燥させ、花粉を採取する。「花粉は葯という袋の中に入っているため、取り出すのに手間がかかる。農家が花粉作りから交配作業まで全てやろうとするととても大変。利用者と一緒に皆で作業することで、その課題を解決できるのでは」とも。
石野さんは「作業の分かりやさなどもあり、利用者が楽しそうに作業していた。この時期、この季節だけの作業だが、皆で農家の手助けができれば」と意気込む。
同取り組みは天気と開花の状況を見ながら、4月中旬まで行う。