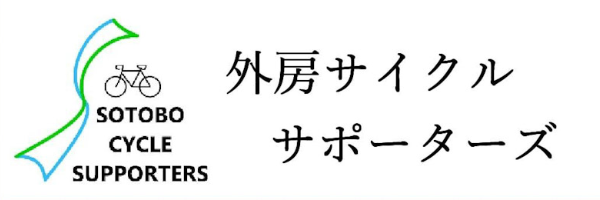長南の笠森観音、高さ16メートルの回廊から「天空の豆まき」

国の重要文化財に指定されている笠森寺観音堂(長南町笠森)で2月2日、「天空の豆まき」が開かれた。
高さ16メールの観音堂の回廊から福引付きの豆をまく僧侶ら(写真提供=笠森観音)
当日は11時から、厄よけの行事として「節分会追儺(ついな)式」の法要を観音堂で行い、申し込みのあった年男や福女、福升や福豆つき護摩札の申込者、来賓などが参列。11時30分から僧侶や年男などから福を分けてもらう豆まきを行った。冷たい小雨の降る中、高さ16メートルの観音堂の回廊から「福は内、鬼は外」のかけ声と共に、3回の入れ替え制で、合わせて1080袋の豆をまいた。そのうち70袋が福引付きの豆だった。約200人の参拝客らは、競って手を伸ばしていた。
住職の小川長圓さんは「この形式で行うのは昨年に続き2回目。上から投げた豆が人に当たっても大丈夫なのかどうかなど、試行錯誤を行い、けがをする人が出ないよう細心の注意を払った」と話す。
福引交換所では、福引と賞品を交換。景品は自転車や家電製品のほか、町内で作られた手作り加工品を用意した。景品を提供した事業所の一つ八兵衛珈琲(コーヒー)焙煎(ばいせん)工房の古市喜章さんは「5年前に店を始めて、中学の同級生である小川住職と約30年ぶりに再会した。地域のためにがんばっている住職を少しでも応援できたらと思い、景品を提供した」と話す。
小川さんは「節分と言えば最近では恵方巻きが有名。元々節分は厄よけの行事。追儺(ついな)は厄を払う意味がある。昔から目に見えない『魔』を鬼に見立て、家の中や人の体に入ってきた『魔』を豆をまいて追い出し、一年間、何事もなく過ごせるように祈る行事を大切にしてもらえたら。国重要文化財の観音堂で行うことで、豆まきの行事を通じて長南町を知ってもらい、来てもらうきっかけになれば」と話す。